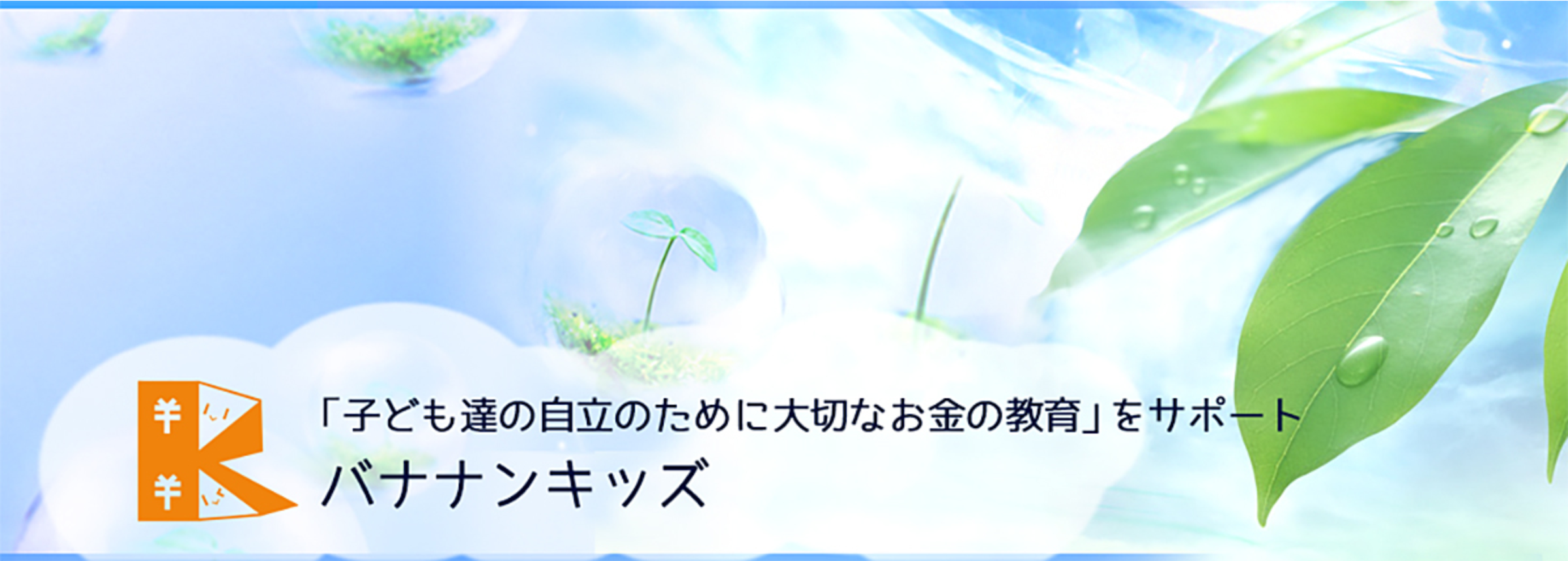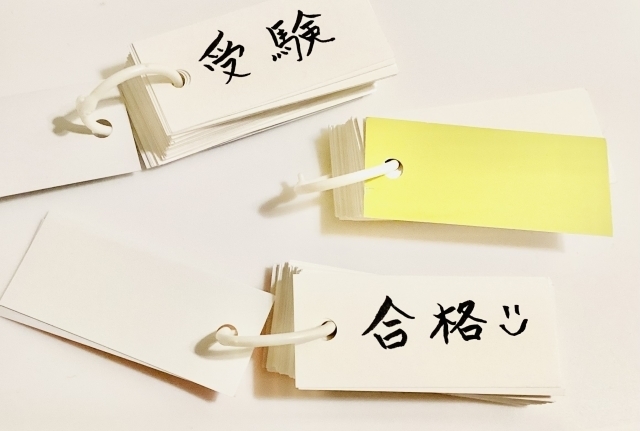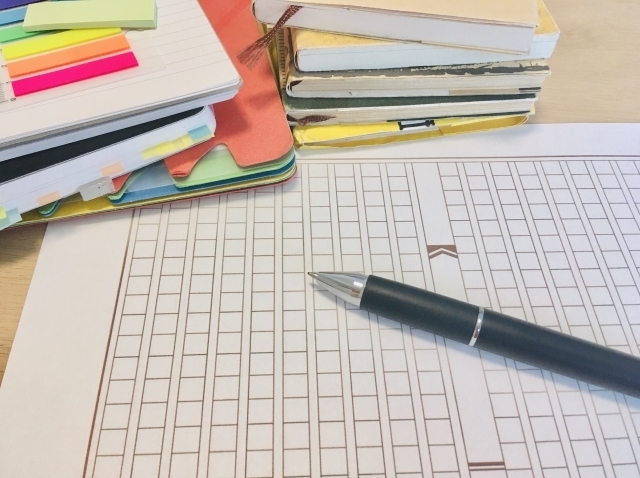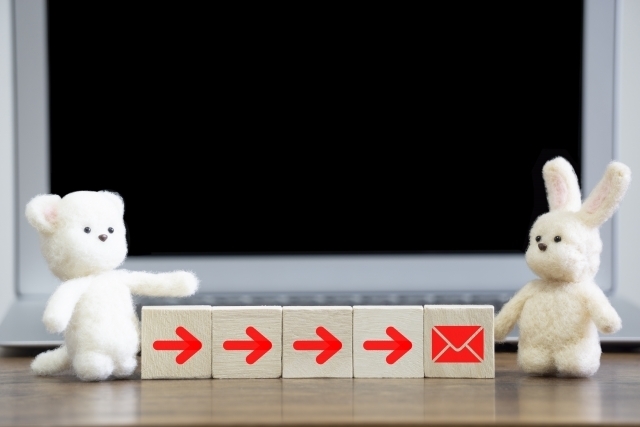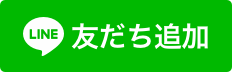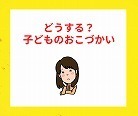子供と青少年の『お金教育の専門家』

「このままじゃ、将来お金で失敗しちゃう!」
我が子のお金のしつけをやり直した体験から、お金の教育が重要だと実感。
15年前から子供たちや親子の「お金の授業」を始め、のべ300校17,000人が受講。
お母さんのための「将来お金に困らない子に育てるお小遣い講座」は道内、オンラインでも人気。
ゲーム形式で学べる講座は、「口で説明するよりわかりやすい」と、学校の授業、大学の講座でも取り入れられ、リピートが多いのも特長です。
- 「講演会で、話を聞いてみたい」
- 「親子レクで小遣いゲームをしたい」
- 「外部講師による授業・講義を考えたい」
という、保護者や教育現場の皆様、お気軽にご連絡くださいね。
- 小遣い制のやりかたがわかり、家庭で取り入れることができる
- ゲームをきっかけに、子どものお金に対する考え方が変わる
- 社会人になっても困らない、騙されない力がつく
お問合せは下記より。
講座や授業など、ご参加いただいた方からの感想
子どものお金の悩み
下までスクロールすると、最近の活動やブログコーナーもあります。
小学生のママ必見‼「我が子をゲーム課金のトラブルから守る方法」
札幌市教育委員会「さっぽろ家庭教育ナビ」より